|
浅草のれん会 |
| 壱の巻 | 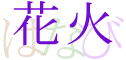 |
|
 昔風に言えば「両国の川開き」でしょうか? 昔風に言えば「両国の川開き」でしょうか?両国の川開き(花火)のはじまりは、享保17年(1732)の大飢饉がきっかけなのです。 全国的な凶作が続き伝染病コロリ(コレラ)が流行、多数の死者を出しました。 享保18年(1733)時の将軍吉宗はその死者の霊を慰め悪霊退散祈願のため「施餓鬼」を催し大川端で花火を打ち上げたのです。 これが世にいう両国の川開き花火の始まりです。 ●その花火、有名なのが“た〜ま〜や〜”“か〜ぎ〜や〜”のかけ声ですよね。 あの玉屋と鍵屋は今で言う花火師の事なんです。 1659(万治2)年、伊賀(三重県)篠原村より弥兵衛という初代が江戸日本橋横山町に花火製造「鍵屋」を興しました。 享保18年(1733)の初めての川開きの花火師が6代目鍵屋弥兵衛。 その時打ち上げた花火の数は20発程度と少なかったそうです(今じゃ2万発の勢いですが・・) それでもその噂は江戸中で評判になり、多くの人を集める年中行事となっていったそうです。 1808(文化5)年ごろ鍵屋に清七という番頭がおり、鍵屋から暖簾をわけてもらい、両国吉川町に「玉屋」を開き玉屋市弥兵衛を名乗ったそうです。 以降、大川端の川開きは両国橋より上流に玉屋、下流に鍵屋がそれぞれ舟を出し、2大花火師の競演となりました。 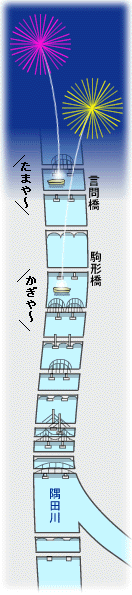 ●はじまりのきっかけは将軍吉宗、しかし「川開き」って言うのは何?と言うと、江戸前期の隅田川には両国・新大橋・永代に橋が架かっていました。そのなかでも両国橋付近はもともと盛り場だったこともあり夏ともなれば涼み客などが集まり、旧暦5月28日から8月28日までは夕涼みの期間とされ水茶屋や物売り、見世物小屋、寄席などが営業していて、その営業を開始しますよと言う日が川開きの日なんですね。 ●はじまりのきっかけは将軍吉宗、しかし「川開き」って言うのは何?と言うと、江戸前期の隅田川には両国・新大橋・永代に橋が架かっていました。そのなかでも両国橋付近はもともと盛り場だったこともあり夏ともなれば涼み客などが集まり、旧暦5月28日から8月28日までは夕涼みの期間とされ水茶屋や物売り、見世物小屋、寄席などが営業していて、その営業を開始しますよと言う日が川開きの日なんですね。そんな「川開き」の日は、舟は全部予約済み、江戸中の舟が隅田川に集まって来て、あまりの混雑に船づたいに向こう岸まで川を歩いていけるといわれたほどの賑わいだったそうです。 そしてその両岸の水茶屋や船遊びの客が川開きの日に花火を上げさせたのが名物となり、川開きイコール花火となっていったのです。 花火、船遊びはこの日を皮切りに、8月28日の打止めまで続いたのでした。 しかししかし、1808(文化5)年頃より続いた2大花火師の競演はあるアクシデントにより幕を閉じます、それは、天保14年(1843)玉屋は失火によリ全焼、町並みを半丁ほども類焼させ、おりしも徳川家斉日光社参の前夜に火事を起こした不運により、所払いとなって廃業。江戸を追放されてしまいました。 1代限りで断絶した玉屋と鍵屋の競演はわずか、35年程で幕を閉じてしまいます。 裏話もあります、実は玉屋の人気は鍵屋を凌ぐほどだったそうです、実際にこの頃の浮世絵の画題になっているのは玉屋ばかりなんですもの。 弟子の「玉屋」のほうが本家である「鍵屋」を上回ってしまい、名実ともに「江戸一番」だったのです。 そんな花火やら船遊びも天保12年(1841)の天保の改革で地味になって行くのでした。 その後中断を挟みながらも続いてきましたが、1961(昭和36)年を最後に交通対策、建物の密集、警備上の問題などを理由に中止が決定し、長い川開きの風物詩もピリオドを打つことになりました。 ●しかし、下町の夏の風物詩として永年にわたって続けられてきた由緒ある行事だけに、浅草を中心とする地元から強い復活の要望が出されていました。 時の都知事美濃部知事は地元の熱意に応え復活に動きました。1978(昭和53)年の事です。 その結果、実施日は7月の最終土曜日の開催とし、打ち上げ場所は言問橋上流400m付近と駒形橋下流200m付近の二カ所に決定されました。 通に言えば言問橋付近の上流は「玉屋(た〜ま〜や〜)」で駒形橋付近の下流は「鍵屋(か〜ぎ〜や〜)」なんですね〜歴史的には・・・ 古式に則り大川端で行われる花火大会の本家本元、隅田川の花火を見ないで花火は語れませんヨ!! ドドォ〜ンと2万発の花火を見ながら「川開き」に酔いしれては如何ですか。 |
||